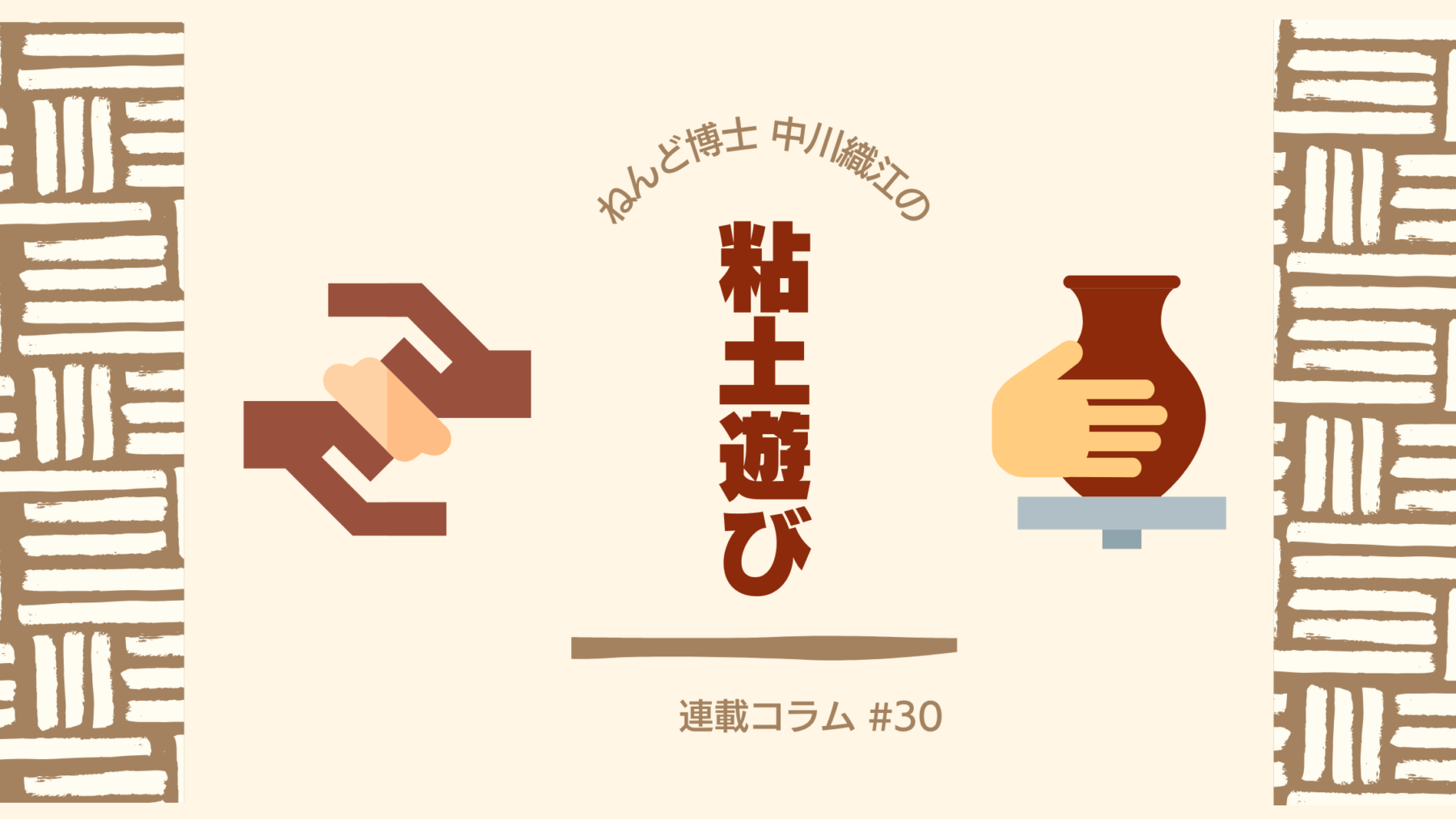今年の夏はどうしようもなく暑かった。はやばやと猛暑予報が出ていたので涼しさを求めて、北海道東部の釧路へ行った。じっさいに行ってみるとさすがに涼しい、寒いくらいだった。
海流がぶつかる地なので、ものすごく霧が深い。しかも海霧だから重たい。夕方あっというまに霧が立ち込めて視界ゼロ近くなるのはミステリアス。朝、光が射してくるとたちまち霧が晴れ、柔らかい青空が見えてくるさまはとてもロマンティック。
霧立ちこめる駅から、夕日で有名なぬさまい橋へ向かって大通りを歩いていくと、右手の方に、ガラス張りのモダンな建物「遊学館」がある。「遊ぶことは学ぶこと」と名付けられた。
建物全体がガラス張りで、中に大きい球体が浮遊しているように透けて見える。それがプラネタリウムで、その下が巨大な砂場だ。素晴らしい。
室内にあるから全天候型で、春夏秋冬365日、晴れても降っても砂あそびができる。
冬、この地は凍土になり砂あそびはできない。だが雪あそびはできる。砂あそびと雪あそびは似ていて、作ってはこわし、こわしては作り、自由にあそぶことができる。とはいえ戸外は寒く、冬は長い。でもこの屋内砂場があればのびのびと全身を使ってあそぶことができる。

建物のドアを開けて入ると、目の前に巨大な砂場が広がっている。吹き抜けで、見上げると4メートル以上も上に、球形プラネタリウムの底が見える。吹き抜け全体の天井までは高さ15メートルある。なんという解放感!ガラス張りだから壁はない。
砂場の広さは130平方メートル。砂の深さは50センチで、砂はゴルフ場のバンカーに使うのと同じ砂を北海道南部にある瀬棚(せたな)の浜から運んできた。
幼児や子どもたちが、父と子が、母と子が、家族3代が、2家族が連れ立ってやってくる。保育園の子どもたちが先生に連れられて入ってくる。手ぶらでやってきて、靴下を脱いだらすぐ砂場へ。バケツもスコップも砂を運ぶ荷車も、小物も備品としてある。

車いすでも、障害があっても大丈夫なようにつくってある。
柱に「すなばのおやくそく」の紙が貼ってあり、
・くつをぬいではいろう
・水をつかわないであそぼう
・はしったり砂をかけあわない
・道具はみんななかよくつかおう
・つくった山、あなはもとにもどそう
・つかった道具はかたづけよう
・すなばからでるときは、すなをはらおう
・すなばのなかではたべる、のむのはダメ×
これだけ。
あとは好きにあそんで、終わったら足を洗い靴下を履いて出ていく。
外を通りかかった人が、砂場であそんでいるようすをニコニコ見ながらすぎていく。あるのが当たり前のようになじんでいる。確実に市民に根付いている。
砂場を囲んでぐるりと広いスぺースがあり、いつでもだれでもご自由にどうぞ、とあちこちにイスとテーブルが置いてある。居眠りしているオジサンもいるし、孫と待ち合わせているオバアサンやオジイサンも、おしゃべりしているママ友たちもいる。わたしは滞在中、何日間もそこへ行って、砂あそびを眺めたり、お茶を飲んだり本を読んだりして何時間もすごした。
この砂場は20年前にできた。
わたしは建設中にここへ来ている。計画段階で知って、行かねば、と釧路へ飛んだ。
砂場プロジェクトの中心は、北海道教育大学・釧路分校(当時)の笠間浩幸さん。
あの時、ヘルメットをかぶり説明を聞きながら、この砂場の広さはギネス級だと話が盛り上がったこともなつかしい。